Crossover Talks 嘉興:ミンスグループ AIスマートマニュファクチャリング実践レポート
Crossover Talks 嘉興:ミンスグループ AIスマートマニュファクチャリング実践レポート
AI導入は、現場で見てこそ本質がわかる。
工場に足を踏み入れ、自らの目で変化を確認する。
近年、AIは産業アップグレードの重要な推進力として注目されています。多くの製造業企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めていますが、真の課題は「AIの重要性を理解すること」ではなく、「いかにAIを現場で実効性を発揮させるか」である。
今回、Profet AI、ミンスグループ(敏実集団)、および寧波スマートマニュファクチャリング産業協会が共催した「Crossover Talks Jiaxing(嘉興)」では、まさにその問いに答える実践的な取り組みが披露されました。
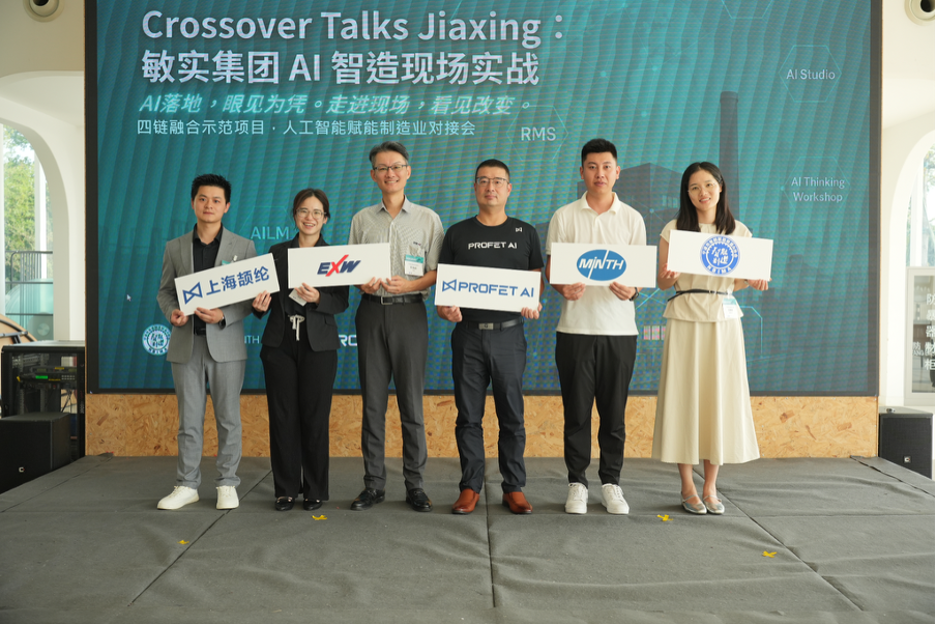
コア知見を生産力へ:ドメインツインによる知識資産化

Profet AI 共同創業者兼 CEO の Jerry Huang 氏 は、製造業が直面する三大不確実性を、中国のSF小説『三体』に登場する「三つの太陽」に例えました。
Huang 氏が指摘する三大不確実性は:関税の変動、地政学的リスク、そしてAI技術の急速な進展である。これらは予測不能に動き続け、まるで「三つの太陽」が不規則な軌道を描くように、製造業もまた不確実性の中で次の一手を模索しています。
こうした環境下で生き残るために不可欠なのが レジリエンス(耐性)強化。そしてその突破口こそが、AIの現場活用にあるとHuang氏は指摘します。
製造業企業のコア競争力は、熟練作業員やドメインエキスパートが持つ暗黙知(調整ノウハウや工法、配合技術)は産業の共識。
そこでProfet AIが提供するのが ドメインツイン(Domain Twin)。
暗黙知をデータモデルへと変換し、場所を選ばず再現可能な「知識資産」として活用できる仕組みです。これにより、個人に依存してきた経験知を確かな生産力へと転換することが可能になります。
経験からデータへ:暗黙知の標準化とモデル資産化

Profet AI プリセールスディレクターのEugene氏は、多くの製造業が直面する課題を次の3つに整理しました:
- 製造プロセス能力の不足
- 新製品開発リードタイムの長期化
- 熟練者退職による現場ノウハウの喪失
この課題に対し、Profet AIの ドメインツイン は新しいアプローチを提示します。
試行錯誤を前提としてきたプロセスを「トレーサビリティを持つかつ標準化可能な知識体系」に変換し、工場データやプロセスパラメータ、ベストプラクティスをモデルに組み込むことで、未経験者でも迅速にスキルを習得できる仕組みを実現します。
「AI導入は複雑なアルゴリズムを理解するから始まるのではなく、まずは現場のペインポイントを明確し、可解釈性と再利用性を備えた解決策に整えることが出発点になる」とEugene氏は強調しました。
成功案例①:卓新通訊 – 良品率35%向上

中国寧波の卓新通訊接插件の副総経理・チェン・イーカイ氏は、同社がAI導入によって得られた成果を紹介しました。
同社は水晶コネクタやLANケーブルを製造しており、従来はリーン生産を推進してきました。しかし、その取り込みだけでは限界に直面。2024年にミンスの未来工場を視察したことを契機に、AIが現地で高い価値を発揮できることを認識し、AIプロジェクトを本格始動しました。
特徴的なのは、一般的な「コース形式のトレーニング」ではなく、13部門合同のワークショップ型アプローチを採用した点です。これにより、AIを単なる知識習得にとどめず、実務に直結する形で現場へ組み込みました。
その結果、C6A FTPプロダクトラインの「アルミ箔除去工程」で良品率を50%から85%へ向上し、月間約100時間の工数削減を達成しました。さらに、企業内で「経験依存型」から「データ駆動型」への文化変革を実現しました。
成功案例②:ミンスグループ – グローバル70工場へ

ミンスグループのデジタルトランスフォーメーションマネージャーのジャン・ビン氏は、グローバル展開を見据えたAI導入戦略について語りました。
同社は2024年に、社内から64件のAI提案を募集。そのうち10件を実運用に落とし込みました。
その代表例が「曲線弧寸法の良品率向上」プロジェクトです。データ収集からモデル構築、現場での検証までを Profet AI AutoMLプラットフォーム 上で実行し、わずか3ヶ月で現場応用を実現。結果としてプロセスの安定性を大幅に改善しました。
さらに注目すべきのは、AIを単なるツールとして導入するのではなく、人材育成を戦略の中心に据えている点です。同社は「社内AIトレーナー制度」を立ち上げ、各地の工場で自主的にプロジェクトを推進できる体制を整備。これにより、グローバル70拠点への水平展開が進められています。
まとめ:AIは現場でこそ価値を生む
今回紹介した事例が示すのは、AIが単なる戦略的スローガンではなく、現場で即効性を持つツールであるという事実です。Profet AI、ミンス、卓新通訊とのパートナーシップ事例は、いずれも「現場のペインポイント」を起点に暗黙知をモデル化し、試験的成果を組織的な能力へと昇華させた好例です。
その鍵となるのが、「現場で見て、現場でAIを使うこと」。
これはCrossover Talks 嘉興が最も伝えたかったメッセージでもあります。
グローバル競争の激化やサプライチェーンの不確実性に直面する日本の製造業においても、こうした 「現場発AI」 のアプローチは極めて有効です。トップダウンの戦略だけでなく、現場主導の実装を通じてこそ、AIは組織全体の競争力を底上げする原動力となるでしょう。
Crossover Talks 嘉興:ミンスグループ AIスマートマニュファクチャリング実践レポート 閱讀全文 »









